第1回:ORC発電事業化備え議論~馬渕工業所~(2025年7月25日号)
馬渕工業所(本社=仙台市、従業員数31人)は、1966年の創業以来、建物の給排水・空調換気設備の設計施工を通し、宮城県を中心に、住宅や学校・病院の建築や、埋設水道管の整備など、まちづくりに貢献している。「熱・水・空気」をコントロールする技術を生かし、独立型ORC発電システム、マブチ・ハイブリットポールⅡ、ENSUS2(リチウムイオン蓄電池)、水道本管工事、修繕保守サービスなどのサービス・製品を手掛けている。
日本生産性本部では2024年、檜作昌史・同本部主席経営コンサルタントが、同社の「ORC発電事業の事業化支援」のコンサルティングを行った。

「独立型ORC(有機ランキンサイクル)発電システム(5キロワット級)」は、80~90度のお湯毎分100リットル程度と20~35度の冷水毎分100リットル程度を装置に流すと、有効電力4・5~5・0キロワット程度が得られるシステムで、NEDO(国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構)の支援のもと、東京大学生産技術研究所や京都大学大学院工学研究科、宮城県産業技術総合センター、イーグル工業と共同開発した。自家消費電力を自由に使えるほか、BCP対策にも有効で、最大約10キロワットアワー超のリチウムイオン電池を搭載し、世界最高の発電効率と省エネルギー化を実現する。
東日本大震災以降、地熱・温泉熱・産業系廃熱などの未利用廃熱を活用した同システム(発電所などが使っている蒸気サイクルの作動媒体を一般的な水から、フロンガスなど、より低沸点の有機媒体に変更し、中低温の熱源であっても蒸気を発生させることで、タービンを回すシステム)が注目を集めている。未利用廃熱の活用策としては潜在需要が大きい一方、5キロワット級の小型ORC発電システム分野では発電した電気の品質条件が厳しく、発電事業者側でこれに対応する必要があることから、コスト増の一因となっており、低コストで高効率な小型ORC発電システムの開発が求められていた。
コンサルティングでは、当初、ORC事業の拡大に伴う資金繰り管理の強化が課題となっていたことから、同社のビジネスモデル、収益構造、キャッシュフローの分析を行い実態を把握したうえで、資金繰り予測を立てる仕組みを運用し、同社に適した資金調達の方法を検討した。また、資金繰りの事務作業が、手作業で手間のかかる方法を取っていたのを改め、エクセルでできるプログラムを作成するなど、効率化を図るとともに事務作業のマニュアル化、標準化を図った。
その後は、社長と定期的に議論し、ORC発電事業の事業化に備えた、分社化やアライアンス戦略、原価設定や売価設定の助言などを行った。
事業化シミュレーションでは、具体的な販売計画や収支計画、原価や売価の設定などについて、3通り(同社が単独で事業化を行う場合、他社と業務提携を行う場合、単独で行うが少し保守的な場合)の案を作り、それぞれの場合のシミュレーションも行った。
埋もれている技術に注目~小野寿光・馬渕工業所代表取締役の話
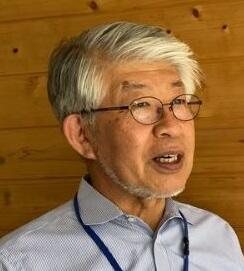
独立型ORC発電システムは、200度未満の膨大な廃熱が捨てられている現状を鑑み、少ない廃水温で発電可能な小型機、自家発電・蓄電の自立運転ができるものを開発した。
技術には革新性、独自性、優位性があり、すでに20社分の納入が進行中で、国内外からの引き合いが拡大中だ。前期の売上は従来の管工事を含め約5.5億円を見込んでいる。ファブレス製造の確立、販売代理店の獲得、メンテナンス網を持つ技術系商社などとの提携を進め、製造・販売・メンテナンス体制の強化を図っている。
ORC発電システムの発電効率は国内最高水準で、熱処理過程がある工場や温泉など熱量が小さい施設でも廃熱を利用できる。工場から排出される未利用熱を活用する発電・蓄電システムとして、脱炭素社会実現に貢献するとともに、災害時などの電力喪失時においても独立して発電・蓄電し、導入先のBCP対策や復元力(レジリエンス性)の高さで社会貢献できることも期待されている。
檜作コンサルには、資金調達の方法やORC発電事業の事業化に備えた助言などをもらった。本業と新規事業のバランスも検討していただいた。今後の当社の方向性のベースを作っていただき、とても感謝している。
今後は、外部企業と提携しながら、当社はエンジニアリングの部分に特化していきたい。「熱・水・空気」の領域はまだまだ開発余地がある。東北大学と行っている熱交換機の開発も進んでいる。同業の大手で製品化されずに埋もれている技術にも注目していきたい。
早期に製品化 数値計画策定~檜作昌史・日本生産性本部主席経営コンサルタントの話
ORC事業はすでに注目されていた事業でもあり、引き合いも多かったので、ある程度、販売の対象先を絞ったうえで、補助金に頼らずに、早めに、製品化して売り上げを計上し、事業化することに留意した。金融機関の支援も必要なので、現実的な数値計画をつくった
今後の同社の課題となるのは営業力だろう。ORC発電システムの営業には専門的な知識が必要になるが、現状では営業できる人は社長を含めて3人しかいないので、他の人もできるように標準化していく必要がある。また、システムを設置するのに配管工事や電気工事が必要となるが、そうした工事を行う事業者とネットワークを広げていくことも重要だ。
一般に、中小企業の事業化においては、往々にして自社の技術や製品の良さに自信を持ちすぎ、甘い見通しを持っている企業が多く見られる。事業そのものは革新的なものでも「うまくいくだろう」と楽観的に考えてしまう場合は、どこかに落とし穴があることが多い。経営コンサルタントなどの第三者が厳しめのことを伝えていく必要があるだろう。
私は指導先に入れば、「あなた方は」「御社は」ではなく、「我々は」という言葉を使い、会社の一員としての意識を持つようにしている。また、元銀行員でもあることから、「多く」「たくさん」「たまに」といった抽象的な言葉は、数字に置き換えるような指導をしている。「ストーリーの無い数字は無意味であり、数字の無いストーリーも無意味である」と言われる通り、結果であり目標ともなる「数字」にはこだわっている。
日頃、経営コンサルタントの後輩には「何でもかんでも自分の得意領域に誘導するな」と伝えている。「自分の得意領域に誘導する」とは、お客様の課題が他にあるにも関わらず、自分の得意領域に課題があると言って、その課題解決を押し付けてしまうことである。会社の自立・自律を指導し、「コンサルタントの要らない会社を目指しましょう」と指導している。自分の得意でない領域には、他の経営コンサルタントに入ってもらうようにしている。それは日本生産性本部のコンサルティング全般に言える。
◇ 記事の問い合わせは日本生産性本部コンサルティング部、電話03(3511)4060まで。
◇ 過去の連載も掲載している、生産性向上のヒントが見つかる情報サイト「生産性navi」もご覧ください。
コンサルタント紹介

檜作 昌史
神戸大学法学部卒業後、旧都市銀行に入社。M&Aアドバイザリー業務や法人向けソリューション営業部門の責任者として従事。
日本生産性本部経営コンサルタント養成講座を修了、本部経営コンサルタントとして、各種事業体の診断指導、人材育成の任にあたる。
(1963年生)
お問い合わせ先
公益財団法人日本生産性本部 コンサルティング部
WEBからのお問い合わせ
電話またはFAXでのお問い合わせ
- TEL:03-3511-4060
- FAX:03-3511-4052
- ※営業時間 平日 9:30-17:30
(時間外のFAX、メール等でのご連絡は翌営業日のお取り扱いとなります)