資源循環経済への「バトンゾーン」、2つの対応 妹尾堅一郎 産学連携推進機構理事長(2025年1月25日号)
連載「続・サーキュラーエコノミーを創る」⑩ 資源循環経済への「バトンゾーン」、2つの対応
はやくも3年半が経った。お陰様で2021年秋から始めた日本生産性本部(経営アカデミー)と私共の産学連携推進機構との共同企画「ビジネスで創る循環経済社会」も順調に回を重ねている。現在、役員を主対象とする「月例研究会」はシーズン7の、また第一線の部課長を主対象とする「資源循環経済対応ビジネスモデル講座」は第7期の、それぞれ真っ最中だ。ご関心ある方は、4月からのシーズン8や第8期へご参加を是非ご検討いただきたい。
資源循環経済への対応は「バトンゾーン」のデザインが重要
これらのホスト講師を務めて気づかされた点は数多くある。本稿では多くの参加者が混乱していたことを一つご紹介しよう。それは、資源循環経済下のビジネスモデルと、線形経済から資源循環経済へ移行する移行転換期のビジネスモデルの二つをゴッチャにしていることだ。二つを区別しないと、混乱して議論が隘路に入り、思考停止に陥ってしまう。
①線形経済(リニアエコノミー:LE)②資源循環経済(サーキュラーエコノミー:CE)③両者の間に設定すべき転換状態(バトンゾーン:BZ)。
①と②を明確にし、その上で、両者を関係づける③のデザインに取り組む。それが効果的・効率的な進め方だ。つまり、線形経済から資源循環経済への移行転換を着実に進めるには、2つの経済モデルの間にある「バトンゾーン」のデザインが肝要なのである。
1つ目は即応的なブリコラージュ的対応
では、どのような方針で臨めば良いか。私は、「ブリコラージュ的対応」と「本格的対応」を併走させる二刀流が効果的・効率的だと考えている。
転換当初はブリコラージュ的対応で構わない。ブリコラージュとは、既に手持ちのモノを寄せ集めて物を作るということで、器用仕事と訳されることもある。これは、もともと文化人類学の巨人であるフランスのクロード・レヴィ=ストロースが提唱した概念だ。世界各地の未開社会では、布の端切れや余り物を使って当面必要な道具を作ったり、ちょっとした壊れ物を解体して新たな日用品を作り出すこと、あるいは本来用途とは関係なく別用途に使用したりすることが普通にある。それを「ブリコラージュ」と呼んだ。
レヴィ=ストロースは、人類が古くから使っていたこのような創造性と機智に溢れる知恵を「野生の思考」と呼ぶ一方で、近代以降のエンジニアリング的な思考(理論や設計図に基づいてモノを作る「設計」や「計画的生産」の思考法)を「栽培の思考(技術思考)」と呼び、二つを対比させた。そしてブリコラージュは、現代にも通用する人類普遍の知恵だと喝破したのである。
ビジネスに即して言えば、ブリコラージュ的対応とは、まず既存・手持ちの要素技術やモノやコトや情報といった資源を従来とは異なる用途(つまり資源循環経済)に使って新たな価値を創発する考え方である。このやり方は、ダメだったら即刻他の手を試せば良いという「アジャイル(素早い)」な試行錯誤を促す方法論であるとも言えるだろう。このように転換移行の前半では、当面できることをまずは試してみるという、「とりあえず、とりつくろう」という対応でも良いのである。まずは取り組んでみることなのだ。
2つ目は本格的なエンジニアリング的対応
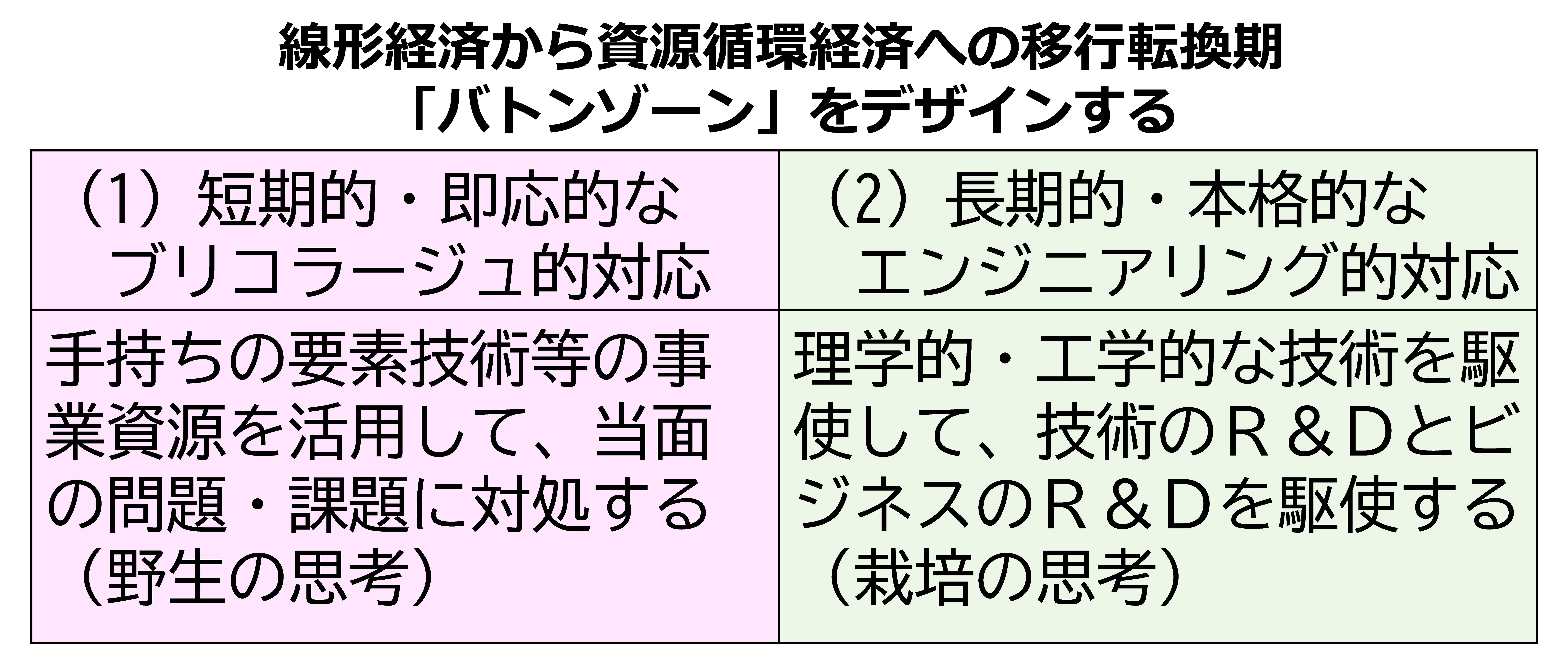
短期的・即応的なブリコラージュ的対応と並行して、長期的・本格的なエンジニアリング的対応も準備する。ブリコラージュ的対応を通じて得られる多くの気づきや学びは、このエンジニアリング的対応に活かせるだろう。あるいは逆に、このエンジニアリング的対応のプロトタイプをブリコラージュ的に試しても良い。
また、技術のR&D(T-rand)だけでなく、ビジネスのR&D(B-rand)も駆使して効果的なビジネスモデル(とそれを支える知財・標準マネジメント)を準備することも重要だ。
整理すると、行うべきは次のようになる。
第一に、線形経済、資源循環経済、線形経済から資源循環経済への移行転換期「バトンゾーン」の、それぞれにおけるビジネスモデルを適切にデザインすること。
第二に、「バトンゾーン」では、一方で短期的・即応的なブリコラージュ的対応を行い、他方で長期的・本格的なエンジニアリング的対応を行う。両者を併走させ、かつ相互に関連づけて組み合わせていくこと。
資源循環経済では、その本質である「資源生産性」を最適化し、そのために「使い続け」すなわち「ユースの延伸とリユースの繰り返し」をビジネスの基本にすることが必須である。そのためには、これらの要点を押さえることを強くお勧めしたい。
著者略歴
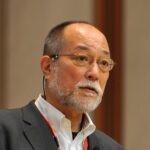
妹尾 堅一郎 産学連携推進機構理事長
慶應義塾大学経済学部卒業後、富士写真フイルム勤務を経て、英国国立ランカスター大学経営大学院博士課程満期退学。慶應義塾大学大学院教授、東京大学先端科学技術研究センター特任教授、一橋大学大学院客員教授などを歴任。企業研修やコンサルテーションを通じて、イノベーションやビジネスモデル、新規事業開発等の指導を行っている。著書に「技術力で勝る日本が、なぜ事業で負けるのか」等。
お問い合わせ先
日本生産性本部 経営アカデミー
WEBからのお問い合わせ
電話またはFAXでのお問い合わせ
- TEL:03-5221-8455
- FAX:03-5221-8479
- ※営業時間 平日 9:30-17:30
(時間外のFAX、メールなどでのご連絡は翌営業日のお取り扱いとなります)