2024年度第4回生産性シンポジウムを開催しました
2025年2月6日
健康いきいき職場づくりフォーラム(事務局=日本生産性本部)は2025年2月6日、2024年度第4回生産性シンポジウムと共催で「2024年度成果発表シンポジウム~ウェルビーイングを重視する健康いきいき職場づくりへ」を都内で開催(オンライン併用)しました。
- ※所属・役職名はシンポジウム開催日時点のものです。
ウェルビーイングを重視する 健康いきいき職場づくりへ

問題提起「健康いきいき職場づくりの新たな歩み」
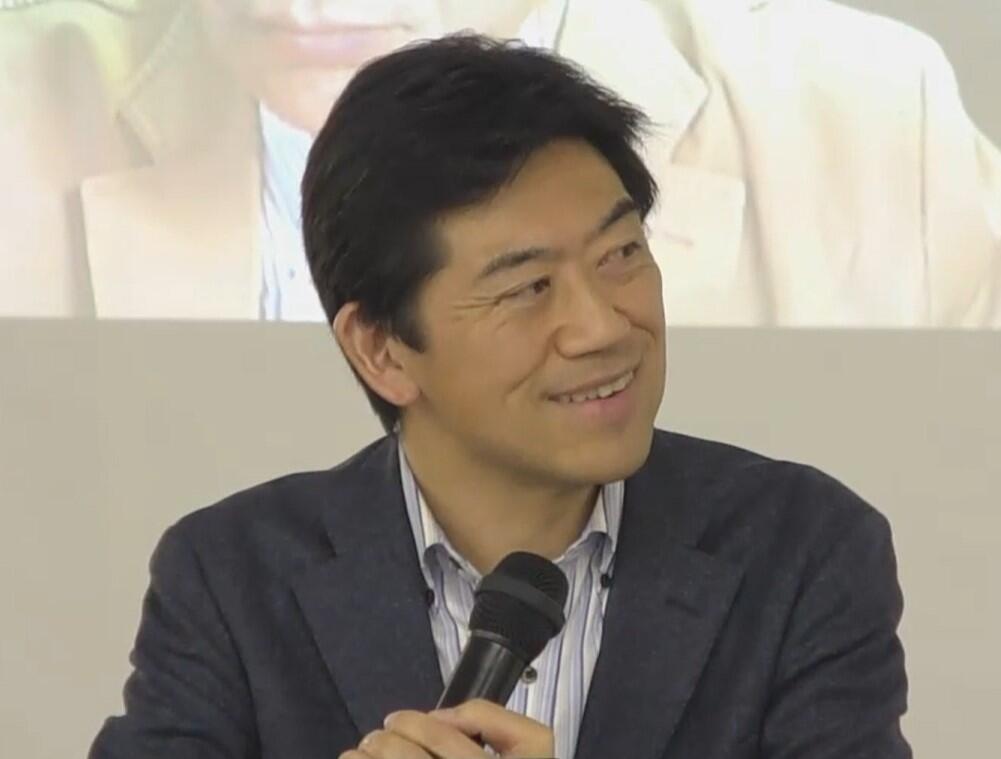
冒頭、同フォーラム代表の島津明人・慶應義塾大学総合政策学部教授が、「健康いきいき職場づくりの新たな歩み」をテーマに問題提起を行いました。
島津氏は、「健康いきいき職場づくりフォーラムは2012年の12月に設立された。設立10年後のタイミングで、これからの健康いきいき職場づくりフォーラムの新しいビジョンとミッションを、『私たちは従業員のウェルビーイングの実現に向けた個人、職場、企業での活動を幅広く支援し、従業員のウェルビーイングの実現に向けた諸活動を支援することを通じ、これからの活動により多くの企業が参画することを目指す。社会全体のウェルビーイングの実現に貢献する』と定めて、様々な活動を展開している。本日のシンポジウムではウェルビーイング経営の枠組み検討や、ウェルビーイング指標の開発についてのこれまでの研究成果を紹介していきたい」と述べました。
成果発表①「ウェルビーイング経営実現のための方法論・枠組み検討分科会報告」
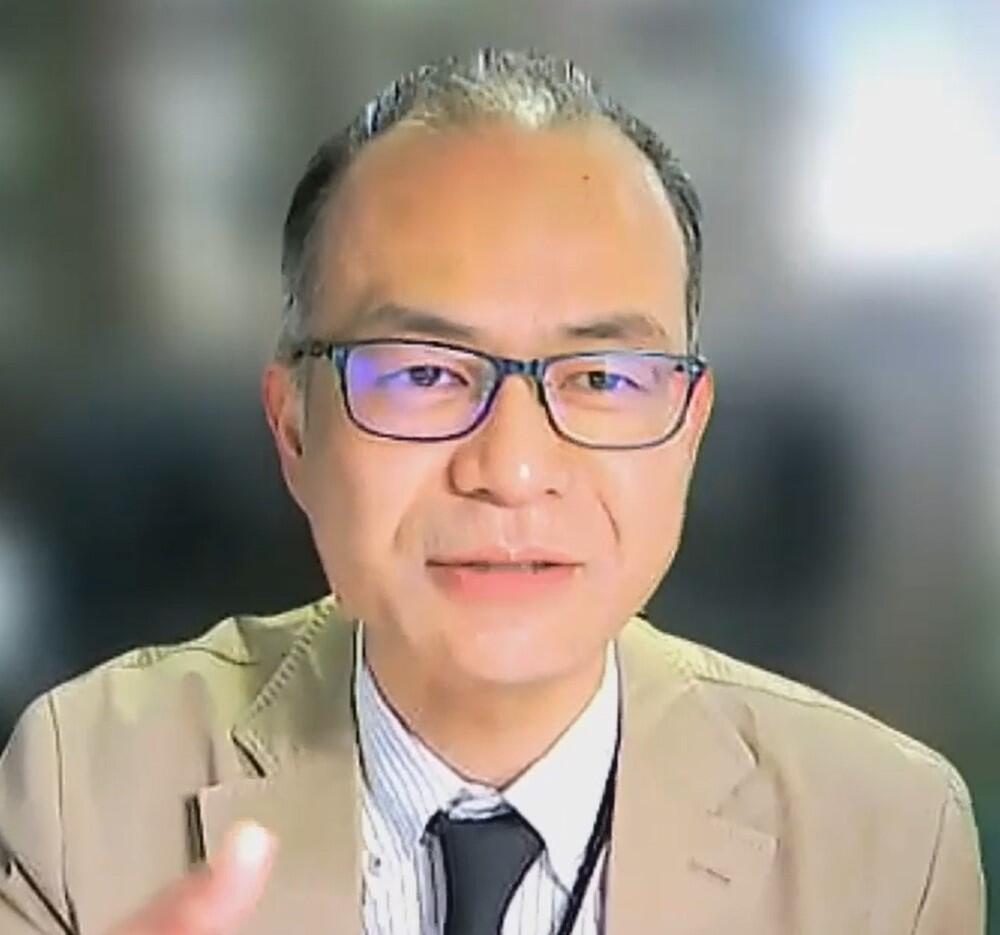
次いで、成果発表①として、江口尚・産業医科大学産業生態科学研究所産業精神保健学研究室教授が、同フォーラムの「ウェルビーイング経営実現のための方法論・枠組み検討分科会報告」を行いました。
江口氏は、「ウェルビーイング経営とは、一人ひとりの労働者のウェルビーイングを高めることを目的とし、職場の安心、労働者の尊厳、つながり(ソーシャルキャピタル)、働きがいを基盤として、生産性の向上と企業の持続的な成長を実現する経営手法だ」と述べました。そのうえで、「ウェルビーイング経営は、従業員が肉体的・精神的・社会的に満たされた状態で働ける環境を整えることを目的としている。単に企業の利益を追求するのではなく、『誰も取り残さない』公平で包摂的な職場づくりを通じて、人的資本を最大限に生かし、社会全体の幸福と経済成長に貢献することを目指している」と説明しました。
また、分科会が提案するウェルビーイング経営の特徴として、個人の幸福だけでなく、職場の「安心」や「ソーシャルキャピタル」を重視することや、「誰も取り残さない」ことを前提としたウェルビーイング経営であること、「ウェルビーイング経営=生産性向上」ではなく、「ウェルビーイング経営=労働の尊厳と社会的包摂と企業の持続的成長の両立」であることを挙げました。
成果発表②「組織と職場のウェルビーイング~ウェルビーイングはどのように業績に結実するか」

成果発表②では、池田浩・九州大学大学院人間環境学研究院准教授が、「組織と職場のウェルビーイング~ウェルビーイングはどのように業績に結実するか」をテーマに、同フォーラムの「指標検討グループ分科会」におけるこれまでの研究成果を報告しました。
具体的には、組織で働く社会人を対象とした計2回のインターネット調査を通して、「ウェルビーイング取組組織」はウェルビーイングに関わる施策や制度をバランスよく、導入している組織であることや、健康や安全、報酬に関わる公正な制度などは、ウェルビーイングを支える基盤であり、これだけでも健康・身体ウェルビーイングや社会的ウェルビーイングを生み出す効果を確認したことを指摘しました。さらに、組織や職場の業績には「職場レベルのウェルビーイングの共有」が強い効果を持つことなどを説明しました。そのうえで、今後は、複数企業を対象とした調査によって、分科会で開発中の個人、職場、組織のウェルビーイング指標を用いた分析を行い、企業ごとに導入している制度や施策、取り組みがどの程度、ウェルビーイングに寄与しているかなどについて検証していくと述べました。
2つの成果発表に対し、3人の有識者からコメント
2つの成果発表については、佐藤光弘・ 富士通ゼネラル人事本部本部長付(健康経営担当)、渡邉和志・ アステラス労働組合中央執行委員長、犬伏真・ 厚生労働省雇用環境・均等局総務課雇用環境政策室室長補佐からコメントがありました。
その後、登壇者6人によるパネル討議「ウェルビーイング経営の実践に向けて」が行われました。
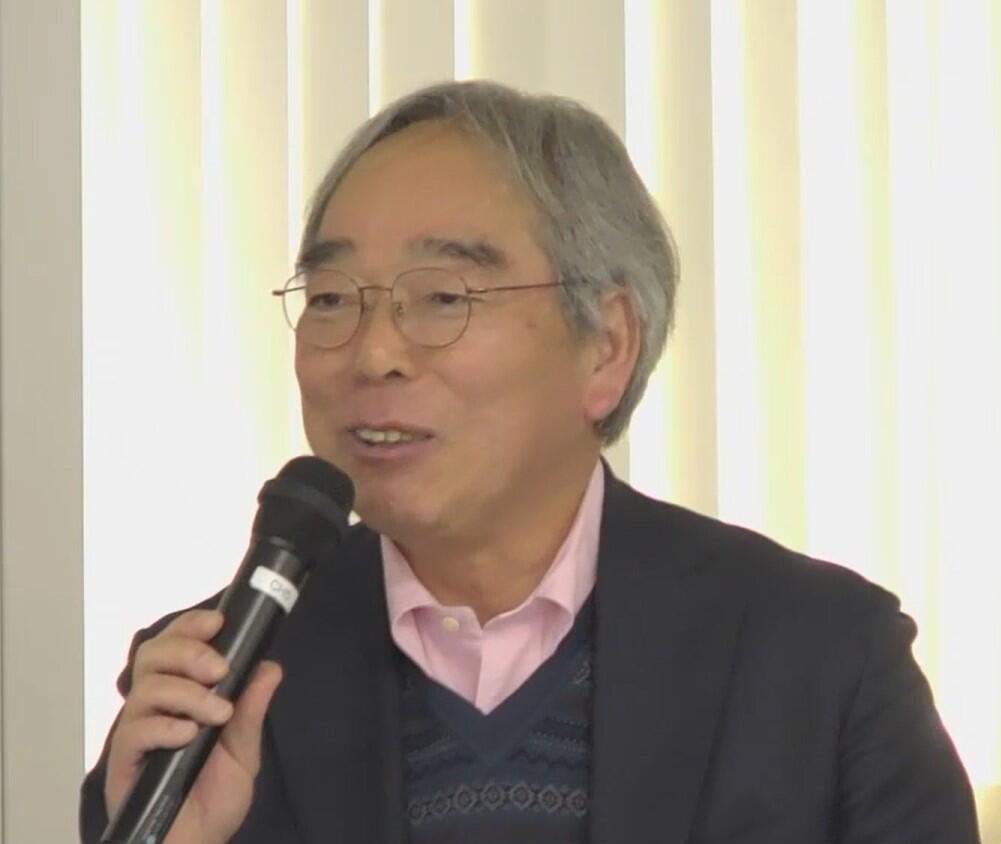


*「健康いきいき職場づくりフォーラム」とは 「労働者の健康」「労働者のいきいき」「職場の一体感」を中核とした「健康いきいき職場づくり」を具現化し、働く人の心身の健康と企業の生産性向上を支援することを目的に、2012年に東京大学大学院医学系研究科精神保健学分野(当時)と当本部が共同で設立。